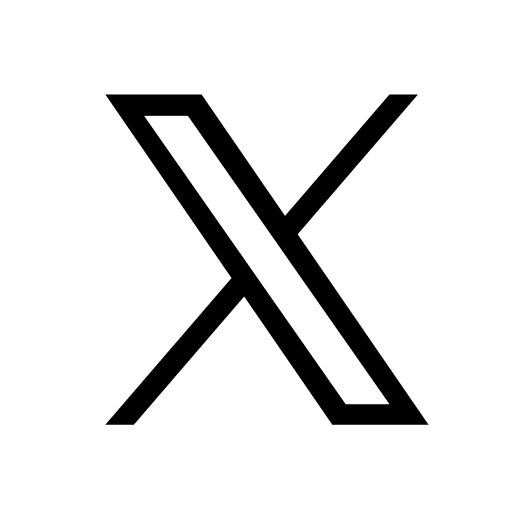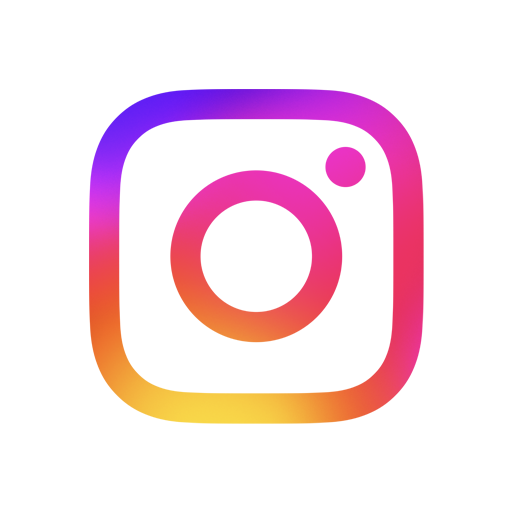誘導をぶっこわせ ~2018年東大理系第2問~

皆さんこんにちは。東進衛星予備校 金沢南校の北川と申します。
不等式証明、難しいですよね。これはたぶん、どのレイヤーにおいてもそうだと思います。
例えば定期テストレベルでも、相加相乗平均の関係式を使った証明や左辺と右辺の差を取る証明が理解できず困る人は少なくありません。或いは大学入試基礎レベル~発展レベルにおいては、そもそも特定の不等式を作って解決すると気づくまでのステップが大変です。それ以上のレベルとなると、有名不等式とされるものが多すぎて見極めにも時間がかかりますし、使い方や考え方の指針が1つも見えないことだってあります[1]。
しかしある程度の知識さえあれば、試行錯誤に幅が生まれやすいのもこのタイプの問題の良いところです。
今回扱う問題は、敢えて誘導に乗らないことによってまた違う世界が見えてきます。どういうことか、実際に挑んでみましょう。
目次
1.2018年東大理系数学第2問(2) ~雑に色々やってみるだけでは難しい~
1.2018年東大理系数学第2問(2) ~雑に色々やってみるだけでは難しい~
今回扱う問題は以下の通りです(※引用注:(1)の省略は引用者によるものです)。
数列\(a_{1},a_{2},……\)を、
$$ \frac{{}_{2n+1}\mathrm{c}_n}{n!} (n = 1,2,……) $$
で定める。
(1) (省略)
(2) \(a_{n}\)が整数となる\(n \geq 1\)をすべて求めよ。
(1)は読み間違いさえなければ簡単な問題なので飛ばします[2]。
(2)をどうするかを考えていきましょう。\({}_{2n+1}\mathrm{c}_n\)と\( n! \)を見比べると、後者の方が素早く増加していきそうです。実際、n=40とかぐらいで比較してみると、
\({}_{81}\mathrm{c}_{40} = 212392290424395860814420\)
\( 40! = 815915283247897734345611269596115894272000000000\)
ですから、40!の方が圧倒的に大きいです。つまり、ある一定以上のnにおいて、
\({}_{2n+1}\mathrm{c}_n < n! \)
が成り立つような気がしてきます。直感的には(n=40の時の結果を見てみても)明らかな気がしますし、この方針で証明することはそんなに間違っていなさそうです。
ですが、そう簡単にことは運びません。
数学的帰納法を使って、例えば\(n=k+1\)のときに両辺をただ引き算してみても、上手くいきません。
ある整数\(k\)が存在して、\(n=k\)のときに\({}_{2k+1}\mathrm{c}_k < k!\)であると仮定する。 このとき、\(n=k+1\)とした式について
\({}_{2(k+1)+1}\mathrm{c}_{k+1} – (k+1)! = \frac{(2k+3)(2k+2)}{(k+2)(k+1)}{}_{2k+1}\mathrm{c}_{k}\)
\(< {}_{2k+1}\mathrm{c}_{k}(\frac{2(n+3)}{n+2} - (n+1))\)
……ほげー
なぜかといえば、\({}_{2n+1}\mathrm{c}_n\)と比べて\(n!\)が大きすぎるからです。
普通、引き算の途中で帰納法の仮定を使う場合は「前に仮定した部分と同じ部分を上手く作ってどうにかする」というのがポイントです。
しかし今回それをしてしまうと、証明したい式の左辺と比べても圧倒的に小さな値になってしまうので上手くいかないのです。
2.Find the f(n)
しかし、考え方としては悪くないはずです。ある値とある値の大小を比べようと思ったとき、今回は直接2つの値を比較しようとすると上手くいかなかっただけで、例えば「何かを間に挟む」などするとどうなるでしょうか?
つまり、\({}_{2n+1}\mathrm{c}_n < f(n) < n! \)を満たす式\(f(n)\)を何か1つ取ってくることを考えます。 このような\(f(n)\)は、例えば次のような性質を満たすはずです。
・ある正の整数\(N\)が存在し、\(N < n\)のとき\({}_{2n+1}\mathrm{c}_n < f(n) \)である。
これをつかって考察します。帰納法で回すときのように、\(n\)を\(n+1\)に変えた式を用意し、二項係数の定義を使って上手く変形すると、こんな感じになります。
\( {}_{2n+3}\mathrm{c}_{n+1} = \frac{2(2n+3)}{n+2} {}_{2n+1}\mathrm{c}_{n} = \frac{4n+6}{n+2} {}_{2n+1}\mathrm{c}_{n} = (4 – \frac{2}{n+2}) {}_{2n+1}\mathrm{c}_{n} \)
つまり、nの値を1増やすことで、\({}_{2n+1}\mathrm{c}_{n}\)の値は4倍より少し少ないぐらいの増え方をするようです。すると、例えば\(f(n) = 4^{n} \)と設定してみるとどうなるでしょうか?
粛々と計算を続けていくと、\(n=9\)のとき、以下のような不等式が成立します。
\( {}_{2×9+1}\mathrm{c}_{9} < 4^{9} < 9! \)
これにより、元の不等式は\(n \geq 9\)のときに対して数学的帰納法を使うことで容易に証明が可能です。
\(n \geq 9\)のとき、\( {}_{2n+1}\mathrm{c}_{n} < 4^{n} < n! \)が成立することを示す。
・\(n=9\)のときについては先述の通り。
・ある整数\(k\)が存在して、\(n=k\)のときに\( {}_{2k+1}\mathrm{c}_{k} < 4^{k} < k! \)が成立していると仮定する。
\(n=k+1\)とした式を考える。まず再左辺と真ん中の値を比較する。
\(4^{k+1} > 4{}_{2k+1}\mathrm{c}_{k} > (4 – \frac{2}{k+2}) {}_{2k+1}\mathrm{c}_{k} = {}_{2(k+1)+1}\mathrm{c}_{k+1}\)
であるから、この部分の大小関係は\(n=k+1\)でも成り立つ。
真ん中と再右辺の値についても同様に考えると、
\( 4^{k+1} < 4k! < (k+1)k! = (k+1)! \)
であるから、これも成立する。□
これが言えれば、特に\(n \geq 9\)について\( {}_{2n+1}\mathrm{c}_{n} < n! \)であることが言えます。
ここまで分かれば、元の問題に戻ることができます。
\(n!\)は\(n \geq 9\)において当然0と等しくありません。なれば、上式の両辺を\(n!\)で割ることで、\(n \geq 9\)について\(\frac{{}_{2n+1}\mathrm{c}_n}{n!} < 1\)が言えます。
\(\frac{{}_{2n+1}\mathrm{c}_n}{n!}\)の分子と分母はともに正の値ですから、\(0 < \frac{{}_{2n+1}\mathrm{c}_n}{n!}\)も言えます。
然るに、\(n \geq 9\)について\(0 < \frac{{}_{2n+1}\mathrm{c}_n}{n!} < 1\)が言えます。0より大きくて1より小さな値は整数ではありえませんから、\(n \geq 9\)の範囲に今回探している\(n\)の値は存在しないことが言えました!
されば、\(0 \leq n \leq 8\)の範囲にしか、今回の答えとなる値は存在しません。8個ならば、愚直に計算したとてそれほど時間はかかりませんね。探してみると、\(n=1,2\)の時に限り\(a_{n} = \frac{{}_{2n+1}\mathrm{c}_n}{n!}\)は整数値を取っていることが分かります。
従って、今回の答えは\(n=1,2\)です。
3.おわりに
どうでしたか?
終わってみると大したことない問題のように思えますが、間に挟む良い値を探してくるのがちょっと大変かもしれません。露骨に分子と分母の桁数が違うので、\(10^{n}\)とかで実験することを思いつくといけるかもしれません。
ちなみに省略されていた(1)の問題については、\(n \geq 2\)において、\(\frac{a_{n}}{a_{n-1}}\)の値がどうなるかを考える問題でした。これを使えば、\(a_{n}\)が一定の値を越えたところで単調減少列であることが分かりますから、同様に適当なところまで計算すれば正解が分かるというものです。
計算の手間はほぼ変わらないので、誘導に乗った方が思考のステップ数が少なく楽でしょう。
まあ、ときにはこういう別解探しも悪くないということで。
今月の記事はここまでです。来月もお楽しみに!
カテゴリ
【記事監修者】塾長 柳生 好春
1951年5月16日生まれ。石川県羽咋郡旧志雄町(現宝達志水町)出身。中央大学法学部法律学科卒業。 1986年、地元石川県で進学塾「東大セミナー」を設立。以来、38年間学習塾の運営に携わる。現在金沢市、野々市市、白山市に「東大セミナー」「東進衛星予備校」「進研ゼミ個別指導教室」を展開。 学習塾の運営を通じて自ら課題を発見し、自ら学ぶ「自修自得」の精神を持つ人材育成を行い、社会に貢献することを理念とする。